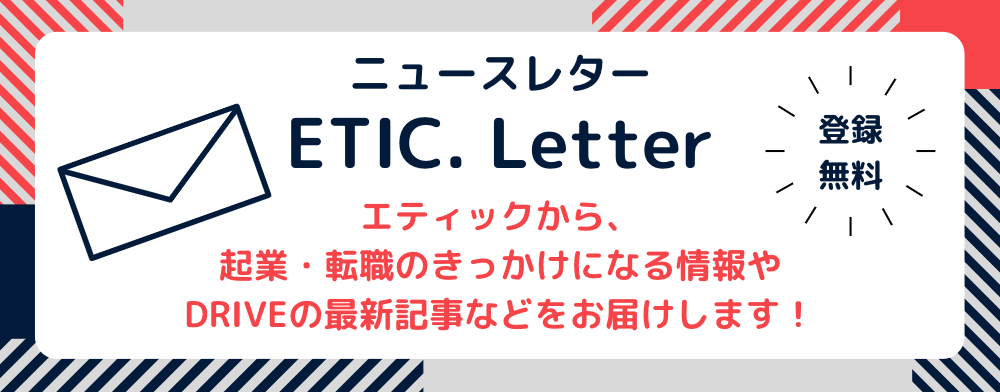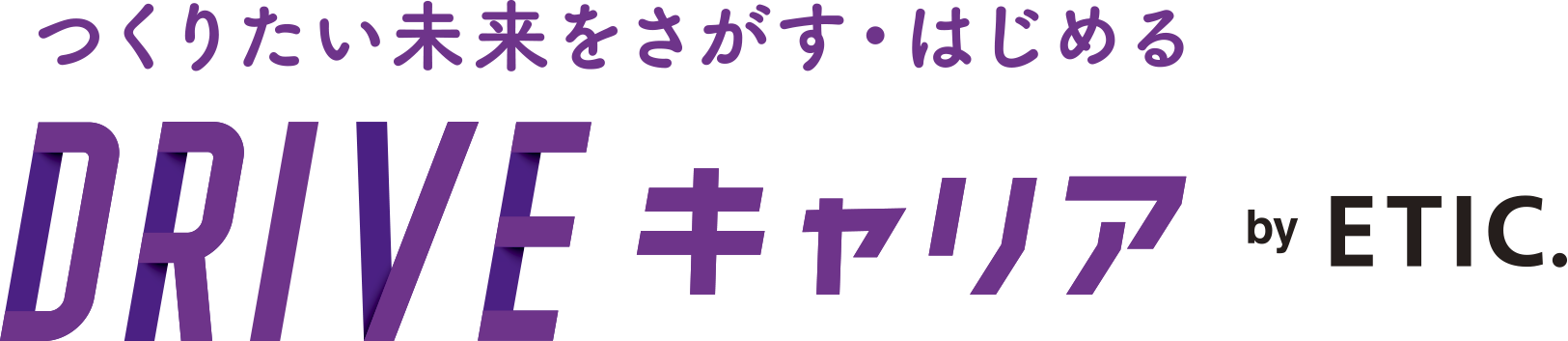「入職が決まった時、うれしくて泣きながら帰りました」と話すのは、昨年4月、子ども支援の団体に入職した玉邑詩織(たまむら・しおり)さんです。
学生時代から「困っている人のために働きたい」と思い続けた玉邑さんにとって、一度は諦めた場所での仕事でした。取材の日、そんな玉邑さんから最初に聞けたのは、「楽しい」の言葉。どんな思いが込められているのか、お聞きしました。
玉邑詩織さん
「人生のトップ3に入るくらい仕事が楽しい」
――玉邑さんが入社してから1年が経ちました。どんな1年でしたか?
楽しかったです。人生のトップ3に入るくらい楽しい1年でした。チャンス・フォー・チルドレン(以下CFC)に入職できたことが本当に大きくて、仕事が楽しいと思えるとプライベートでも前向きになれて、好循環が起きているのを感じます。
――CFC入職後、広報ファンドレイジングを担当されていますが、前職では中高校生向け教材の編集者としてプロジェクトマネジメントを担われていました。民間企業とソーシャルセクターとの大きな違いを感じることはありますか?
前職での私の役割は進行管理が中心で、教材のプロジェクトをいくつか同時に動かしていました。予算管理、外部関係者の方々とのコミュニケーション、研修や講演の企画、発行日や原稿納品、会議の日程調整や進行管理、校閲などをスケジュール通りに進める職人的な仕事でした。
CFCでは、とにかく多種多様な仕事が“飛んで”きます。業務的には、寄付者の方とのコミュニケーションや法人営業、イベント企画運営、WEBサイトのリニューアルなど幅広く、自分でも挑戦したいので“取りに行く”うちに守備範囲が広くなったと思います。
初めての仕事が多いのですが、私自身、新しいことが好きなので、何でも飛んでくる状態がすごく楽しくて、どう進めようかと考える状況にもワクワクしています。
――「仕事が楽しい」と思える状態は、多くの人が望んでいることだと思います。玉邑さんが楽しいと思える時は、具体的にどんな時ですか?
最近だと、コロナ禍がようやく落ち着いてきて、寄付者の方々と直接お会いできる機会づくりが増えたことがうれしいし、楽しいです。寄付者の方たちとお会いすると、「やっと会えた」と思えます。
とにかく、みなさんからびっくりするくらい温かいメッセージをたくさんいただくのですが、寄付だけでなくボランティア活動に参加してくださる方もいらっしゃるんです。「こんなに素敵な方々がCFCの活動を応援してくれているんだ!」と実感できる瞬間に立ち会えることがとにかく楽しいし、やりがいにつながっていると感じています。
大学を1年間休学して、島根県の町営塾でインターン
――玉邑さんは、大学時代から教育格差の課題に関心をお持ちでした。どんなことがきっかけだったのでしょうか。
両親が教育福祉の分野で仕事をしている影響が大きいです。特に母は、ソーシャルワーカーとして生活保護を受給しているご家庭の訪問、保護者や子どもの相談支援などに関わってきました。母はもともと父と同じ障がいのある方が暮らす福祉施設の職員として働いて、その後、教育委員会や児童相談所で子ども支援をしていました。
子どもの頃は、毎年、福祉施設が開催するお祭りやイベントに連れて行ってもらっていて、父と母が施設に暮らす方と接する姿もよく見ていました。自宅でもよく仕事を通じて感じたことなどを話してくれるような両親だったので、私も自然と、「仕事とは困りごとや生きづらさを抱える人たちのために働くことなんだ」と思うようになりました。
――大学時代には1年間休学して教育現場でインターンをしたそうですね。
大学3年生の時、ゼミや母の仕事の影響で地域間の教育格差や子どもの貧困を解消する仕事に関心を持ち始めたのですが、「何も現場を経験していないのにいきなりその仕事に就くって矛盾していないだろうか?」と疑問が湧いて、1年間、インターンを経験しました。
インターン先は、情報収集中にたまたま地域間の教育格差解消に取り組む企業のWEBサイトを見つけて、一度見学に行き、そのまま決めました。
そこは、島根県の津和野町で高校魅力化プロジェクトに取り組む津和野高校で、高校の敷地内で中高生向けの町営塾を運営していました。私は、町営塾のスタッフとして、授業のサポートほか、生徒からの勉強の相談にのっていました。
玉邑さんがインターンした島根県・津和野町。緑豊かな美しい風景が広がる
公教育機関の学校と民間企業が協力し合って、子どもから大人までいろいろな人が混ざり合って学ぶ、この環境に「ここにしかない体験ができるはず」と魅力を感じたのですが、貴重な経験がたくさんできました。
大手出版社で公教育の教材制作・開発を経験
――大学卒業後は、教育系の大手出版社に就職されました。教育への関心を活かした形で仕事の経験を積まれたのですね。
昔から、いろいろなセクターの人をつなぐ立場で仕事がしたいと思っていました。自分に向いているし、絶対に前進できる気がしていたんです。同時に、仕事の基本を学びながら経験と視野の幅を広げたい、公教育に関わりたいという思いから、公教育に向けて広く事業を展開していた前職で働くことになりました。
教材制作に携わった3年間は、自分の親よりも年上の専門家たちと会議で議論したり、課題解決のための問題設計の検討を進めたり、また教材の開発などたくさんの経験をさせていただきました。
ただ、一方で困っている人をサポートする仕事に就きたいという学生時代からの思いが諦められず、子どもの貧困や教育格差に対する関心も深まっていました。
普段、情報収集する時には教育の課題解決にアンテナが向いているのですが、ある時、たまたま教育系WEBメディアの求人情報が目に入って、DRIVEキャリアコーチングを知り、ソーシャルの仕事について話を聞いてみたいと思って申し込みました。その時、紹介されたのがCFCでした。
CFCへの入社が決まった時、うれしくて泣きながら帰った
――DRIVEキャリアコーチングでの玉邑さんは、教育格差への関心が高いこと、「困った人のために働きたい」という働く目的が明確でした。編集者としての経験もプロジェクトマネジメントとして活かせる要素が充実していたので、教育格差解消の仕組みづくりで社会的インパクトを出しているCFCの仕事が参考になりそうだと思い、ご紹介していました。CFCについて、玉邑さんはどんな印象でしたか?
実は、CFCの活動自体は大学生時代から知っていました。ちょうど渋谷区でスタディクーポンの取り組みが始まった頃にそのニュースを見て、「すごくおもしろい取り組みをしている団体がある!」と印象に残っていたんです。
当時、スタディクーポンの仕組み作りにも興味を持っていました。私は子どもの頃から作戦や戦略を考えるのが好きだったので、もしかしたら活かせるかもしれないと思ったんです。CFCの求人情報も調べましたが、新卒採用はしていなかったので「無理だよな」と諦めていました。「でも、いつか何かの形で関わりたいな」とも思っていました。だから、DRIVEキャリアコーチングでCFCのお話が出た時、勝手にご縁を感じていました。
チャンス・フォー・チルドレンが発行するスタディクーポンの仕組みを図で表したもの
――その後、CFCへのエントリーを決めました。どんな思いだったのでしょうか。
教育課題の解決に取り組むNPOやソーシャルベンチャーの中でも、CFCは私にとって特別でした。CFCのミッションは、「多様な学びを すべての子どもに」ですが、私が学生時代に自分が仕事でやりたいことを言語化した思いとほぼ同じだったんです。当時、私は、生まれた環境や特性に関わらず、やりたいことができる社会にしたいと思っていました。だから、CFCのビジョンとミッションを知った時、「もうここしかない」と思いました。
採用が決まった時のことは今でも覚えています。残業を終えて帰宅している途中、スマホに「内定が決まりました」という通知が届いて、うれしくて泣きながら帰ったんです。
ファンドレイジングをもっと極めて、天職にしたい
――CFCの仕事では自分から何か新しく企画を始めることはありますか?
この数年は社会人ボランティアの活動が新型コロナウイルス感染症拡大の影響でストップしていたのですが、最近、ようやく運営できるようになったので、今後の方針や企画運営で自分からメンバーに働きかける場面が多いです。また7月に新規事業を立ち上げる予定なのですが、WEBサイトの構築や支援者の方に向けたイベント開催などいろいろ新しく企画を始める予定です。
今回の新規事業は、代表理事の今井や奥野をはじめ幹部メンバーが2年ほどかけて準備を進めてきたものを世に出すのですが、私は、これまでの事業の変遷をキャッチアップしながら、広報物の制作や資金調達にかかわる業務の進行管理をしています。
具体的には、プロジェクトの課題や優先順位に合わせて自分でスケジュールを立てて、進め方を上司に相談したうえでアクションを起こしています。CFCに入職した当初から、メンバーのみなさんは仕事の大小関わらず、相談しながら進めるのが自然に行われていて、私もすごく相談しやすいです。
――前職の経験が活かせていると感じることはありますか?
多々あります。今担当している仕事の肝になっているのは、すべてマネジメント力です。いろいろな人との関わり、イベントやWEBサイトの企画運営など、前職のプロジェクトマネジメントの経験を期待されていると思っていますし、大きなベースになっていると感じます。
――自分の経験を、社会をつくる仕事に活かしたい、でも本当に活かせるのだろうかと思う人は多いと思います。そんな人に向けて、玉邑さんならどんな言葉をかけますか?
例えば、私なら前職での教材制作など、担当業務をそのまま活かすことは難しいと思います。でも、プロジェクトマネジメントというように抽象的に言語化できると広く活用できると思っています。一度、ご自身が日々進めている仕事を見直してみるのはいかがでしょうか。
実は、前職の先輩から「自分の汎用的なスキルは何だろうって常に考えておくといいよ」とアドバイスされていたおかげで、私もそういう見方ができるようになったんです。活かせないスキルはないと思っています。だから、まずは目の前の仕事をしっかりと進めることがとても大事なんだと思います。
――今後、5年先、10年先はどうなっていたいと思いますか?
ファンドレイジングという仕事について、天職かもしれないという感覚があります。活動を応援してくださる方々との出会いを増やせるいい仕事なので、もっと極めていきたいです。
自分に必要な経験としては、ゼロから事業を立ち上げることに携われると見える世界も変わってくるだろうと思っています。また、以前から海外の教育支援にも関心があるので、いつか先進的な取り組みをしている国に行って、仕事の経験を積みたいです。そのためにも、今は、特にビジネス英語が不安のないレベルにまで上達するように英語の勉強を頑張ります。
<玉邑さんの上司 チャンス・フォー・チルドレン 高田絵梨さんから一言>

ファンドレイジングチーム リーダー 高田絵梨さん
玉邑さんが入職してからこれまで、情報発信の主軸であるWEBサイト改訂や大規模イベントの企画運営など、重要かつ難易度が高いプロジェクトを中心となって引っ張っていく姿を隣で見て、頼もしい仲間ができたことを心から嬉しく思っています。
また、日頃からこぼれ落ちそうな業務を逃さず対応していること、相手に寄り添った丁寧なコミュニケーションをとっていること、そんな玉邑さんの相手を尊重し、真摯に業務に取り組む姿勢は、チームにとって良い刺激となり好循環をもたらしてくれていると感じています。
これからも、応援してくださる方々と共に活動を広めていけるよう、一緒に頑張っていきましょう!

東京スカイツリーをバックにCFCメンバーのみなさんと。玉邑さんは左端。左から3番目は代表理事の今井 悠介さん
※記事の内容は2023年5月取材時点のものです。
※写真提供 : 公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン
<子どもの体験奨学金事業「ハロカル」クラウドファンディングのお知らせ>
チャンス・フォー・チルドレンでは、2023年7月4日、子どもの学校外のスポーツや文化芸術活動、キャンプ、旅行などの「体験機会」の格差の解消を目指して、子どもの体験奨学金事業「ハロカル」を始めました。全国へと展開する新事業の発足に伴って、同日からクラウドファンディングも行っています。
▽「体験格差」をなくすため、 全国の子どもに「体験奨学金」を届けたいhttps://readyfor.jp/projects/halocal2023
開始後たくさんの応援が集まっています。ご関心ある方はぜひのぞいてみてください。
公益社団法人 チャンス・フォー・チルドレンでは、ただいま一緒に働く仲間を募集中です。ご興味ある方は、下記のDRIVEキャリア求人記事をご覧ください。
公益社団法人 チャンス・フォー・チルドレンの人材募集の詳細はこちら!
ソーシャルセクターへの転職にご関心ある方は、経験者の方たちのインタビュー・関連記事もあわせてお読みください。
公益社団法人 チャンス・フォー・チルドレンに関する記事はこちらです。ご関心を持たれた方、ぜひ様々な角度からCFCの魅力に触れてください。
>> チャンス・フォー・チルドレンがもっと深くわかる厳選記事
あわせて読みたいオススメの記事
#ワークスタイル

#ワークスタイル

スキルではなく「興味・共感」が求められた先に、10年後の人生の可能性が見えてきた
#ワークスタイル

#ワークスタイル

#ワークスタイル


イベント
【採用募集説明会開催!】NPOカタリバ連携自治体・北海道下川町から、地域おこし協力隊(地域共育コーディネーター)を募集!
北海道/オンライン
2024/04/24(水)?2024/04/25(木)

事業支援
地域・社会課題解決ビジネス応援融資(愛称:S-wish)の第5回の申込を受付中
東京都/東京都(島しょ地域を除く)および埼玉県・神奈川県の一部 / 当金庫の各店舗の営業地域内
2024/05/01(水)?2014/07/31(木)


イベント
エンドオブライフ・ケア協会設立9周年シンポジウム いつか当事者になる「わたし」へ ~認知症当事者と子どもたちの語りから学ぶ~
神奈川県/ウィリング横浜12F &オンライン
2024/04/13(土)?2024/04/13(土)

イベント
Social Impact Day 2024『インパクト・エコノミーが実現する”システム・チェンジ”』
東京都/笹川平和財団ビル11F 国際会議場(および オンライン)
2024/05/15(水)?2024/05/15(水)